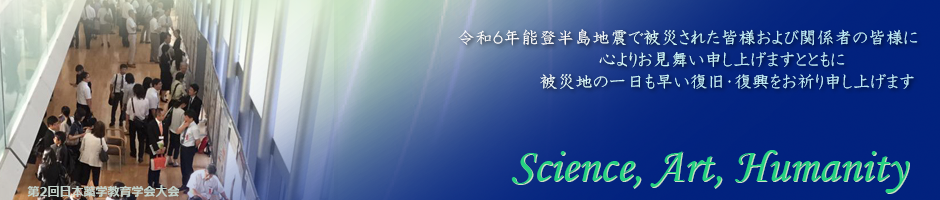一般社団法人化について
日本薬学教育学会
会員各位
代表世話人 乾 賢一
拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、昨年の日本薬学教育学会第2回総会にてご承認いただいた通り、現在、一般社団法人日本薬学教育学会の設立に向け、準備を進めております。
会員の皆様に、法人設立手続きの経緯と新定款(案)および設立時役員についてあらかじめお知らせ申し上げます。
9月1日(土)に行われる第3回総会を前に、以下の文書等につき、あらかじめご高覧いただけますと幸いに存じます。
敬具
■法人設立の流れと会員の皆様の移行について
現在会員の皆様におかれましては、一般社団法人成立の際、それぞれ当法人の個人会員、機関会員、賛助会員並びに学生会員として入会したものとみなされます。※新たにご入会のお手続きをしていただく必要はございません。
任意団体日本薬学教育学会の解散および一般社団法人日本薬学教育学会設立の流れを以下の通り図式化いたしましたのでご確認ください。
一般社団法人への移行
■設立時役員について
設立時代表理事(理事長):乾 賢一(京都薬科大学)*
設立時理事:有田 悦子(北里大学)
設立時理事:石井 伊都子(千葉大学医学部附属病院)
設立時理事:石川 さと子(慶應義塾大学)
設立時理事:入江 徹美(熊本大学)*
設立時理事:小澤 孝一郎(広島大学)
設立時理事:亀井 美和子(日本大学)
設立時理事:木内 祐二(昭和大学)
設立時理事:小佐野 博史(帝京大学)
設立時理事:鈴木 匡(名古屋市立大学)
設立時理事:永田 泰造(日本薬剤師会)
設立時理事:中村 明弘(昭和大学)*
設立時理事:西口 工司(京都薬科大学)
設立時理事:長谷川 洋一(名城大学)
設立時理事:平田 收正(大阪大学)*
設立時理事:安原 智久(摂南大学)
設立時監事:市川 厚(武庫川女子大学)
設立時監事:小池啓三郎(日本私立薬科大学協会)
以上18名 (*…設立時社員)
■新定款(案)
こちらより内容をご確認ください。
■お問い合わせ
ご意見やお気づきの点があれば、【8月14日(火)】までに事務局宛(jsphe@asas-mail.jp)に下記のフォームを利用してご返信ください。
日本薬学教育学会は、新しい薬学教育の発展・充実に向けて2016年8月に発足し、2018年10月には一般社団法人となり、科学的基盤としての薬学教育学の確立を目指して活動を続けてきました。本学会は、学術大会の開催と学会誌「薬学教育」の発行を重要事業として活動内容を充実させながら着実に発展し、2021年7月現在、個人会員678、学生会員56、機関会員66、賛助会員8を数えています。この間の会員並びに関係者の皆様のご尽力に感謝申し上げます。
昨年2月以来、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)拡大に伴い、社会活動が激変し、大学においても未曾有の事態が続いています。感染防御のために、対面式の教育、研究、学術活動は転換を余儀なくされました。各大学では、薬学教育モデル・コアカリキュラムに沿った教育が実践されてきましたが、従来の講義、演習、実習などをコロナ禍において如何に対応するか、オンライン講義などICTを活用した創意工夫と挑戦が始まりました。2006年から本格的に始まった薬学教育改革の経験・実績を礎に、コロナ禍での試行錯誤を重ねながら最大限の教育効果を得る努力が続けられてきました。一方,日本薬学教育学会第5回大会は、昨年9月に帝京大学薬学部の大変なご尽力によってWeb(ライブ&オンデマンド配信)で開催され、これまでの大会とは異なった新たな成果も生まれました。このような背景から、学会誌編集委員会では、危機的状況下における薬学教育実践例の収集・提供は本学会の使命と位置付け、様々な教育・医療機関における教育上の取り組みや実践例を学会誌「薬学教育」に投稿いただくよう呼びかけを行いました。幸いにも15編の論文が集まったことから、特集「COVID-19パンデミック下での薬学教育~レジリエントな教育システム構築に向けて~」を発行することができ、「薬学教育」のJ-STAGE電子ジャーナル公開システムに掲載されています。同時に、薬学教育に関する貴重な資料として会員、薬学関係者に広く活用していただくために、別刷を発行することにしました。コロナ禍における薬学教育の展開や検証を行う上で、各大学の経験・実績に加えて、本特集に掲載された論文が新たなアイデア源になることが期待されます。薬学教育において、対面式教育の必要性・重要性は言うまでもありませんが、オンライン講義やウェビナーなどICTを駆使した教育活動、学会活動は、アフターコロナの時代においても形を変えながら活用され、新たな教育効果が生まれるでありましよう。
現在、薬学教育モデル・コアカリキュラム(2013年改訂)は、次期改訂に向けた文部科学省調査研究事業が進められており、2022年度には薬学に加えて、医学・歯学も同時改訂される予定であります。医療の分野は、近年専門分化と同時に高度化が進んでいますが、チーム医療の推進等の観点から、医学・歯学・薬学の卒前教育においては、医療人として共有すべき価値観を盛り込むなど、整合性のとれたカリキュラム内容となることが求められています。一方、厚生労働省の「薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会」においては、薬剤師に求められる役割、今後の薬剤師の養成や資質向上等の課題について、需給推計を踏まえつつ検討した結果を取りまとめ公表されました(2021年6月)。患者に寄り添う、質の高い薬剤師の養成を目指して、6年制薬学教育が始まり、2015年から改訂薬学教育モデル・コアカリキュラムが実施されています。しかし、社会情勢やニーズ、経済・財政・社会保障などの諸問題を背景に、文部科学省、厚生労働省では上述のように薬学教育や薬剤師に係る議論が進められています。日本薬学教育学会は会員の要望に応えるべく、薬学教育のプラットホームとして活動を続けていますが、今後、日本医学教育学会をはじめ、医療系教育学会と連携を深めながら、医療プロフェショナリズム、多職種連携教育(IPE)などの教育にも貢献する必要があります。
2006年にスタートした6年制薬学教育は15年が過ぎ、既に第10期の卒業生が社会に巣立っています。コロナ禍が続く困難な時代の中で、薬の専門家としての薬剤師の役割は一層明確になってきました。今、薬系大学の教職員、学生、並びに薬剤師、ファーマシスト・サイエンティストに求められること、それは「6年制薬学教育の責任と矜持(自信と誇り)」であります。薬学・薬剤師の社会的評価を高めるためには、関係者の更なる自覚と覚悟を期待したいと思います。